Journal
玄関先の雑談がねむくなる
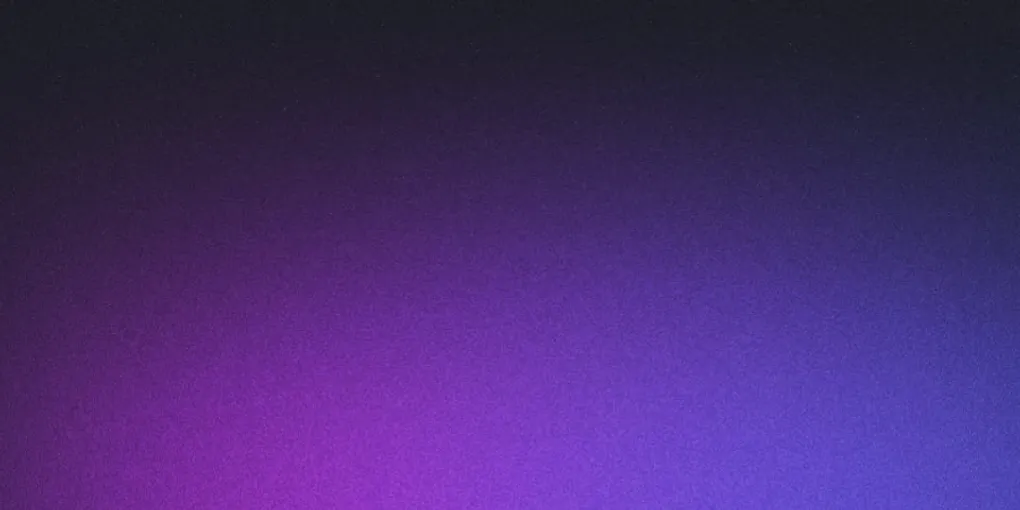
玄関先の談話が少なくなって久しい。
わたしがもっと小さい子どもだった2000年代頃、つまり『前SNS時代』までは、そこかしこで井戸端の談話が繰り広げられていた気がする。
母や知り合いのおばちゃん、祖父母や親戚の会話が、退屈した空気の中で独特のくぐもった響きを帯びていた。
冬の陽だまりの座布団で、茶菓子もお茶も全てなくなってしまって何もすることがないのに、大人たちの伸び切った母音やノイズカットされた子音を耳にしている。
頭がわれそうなぐらい退屈でねむたいのに、帰ることはゆるされない。
かなり個人的なのだけれど、私がこのような感覚になるのは、たいてい冬である。カラッと晴れた陽だまりであることが多い。
もしかしたら、親戚が集まりやすい冬に退屈することが多かったからかもしれない。冬特有の冷たさと、陽だまりの面熱が同時に思い起こされる。
私は最近、あまりこういう感覚におちいることはないけれど、ときどきある。街中でおばちゃんたちが立ち話しているのを聞いたり、YouTubeで昔の映像を見たり(NPO法人科学映像館とか)、ポツンと一軒家を見たりした時だ。
フラッシュバックは、まず視界の損失から始まる。視界の端の方から、無数の色点が混交して暗色になった半透明のノイズが、視界中心部に向かって急速に範囲を拡大する。
スーラの点描絵画を思い浮かべるとわかりやすいだろう。つまり、一時的に視界が全て半透明な黒いものに覆われる。焦点の緊張がほどけ、内耳の平衡感覚が一瞬後ろに後退する。
眼底のあたりから脊髄に向かって、独特の熱を帯びた感覚が走る。該当する記憶は、この辺りで数クリップのビデオとして再生されたのち、また感覚はもとの鋭敏な状態に戻る。
高専に入学して、音響や信号処理をつまみ食い(専門ではない…)するようになってから、ふとあの時の眠気の正体について考えることがある。
あれは、単なる退屈さだけではない。物理的な音の特性が関与しているのではないか、ということだ。
たとえば、あの眠気を誘う音響の正体は、障子やふすま、あるいは距離という物理的なフィルタにあるのではないだろうか。
人間の言葉の意味を決定づけるのは、子音(k, t, s)の高い周波数の成分だ。しかし、隣の部屋や玄関先から漏れ聞こえたり反響したりする会話は、壁や空気の減衰によって、この高周波成分が削ぎ落とされている。
結果として、耳に届くのは「あー」「うー」「んー」といった、伸び切った母音の低い響きだけになる。これは、意味を持たない「音の波」であり、脳は言語処理(デコード)をあきらめて、ただの振動として受け入れ始める。
方言が入っている可能性があるのも、注目すべき点だ。私の母語である標準語は、比較的音程の変化が平坦であり、どちらかというと子音の種類で音声を読み取っている感覚がある(あくまでも標準語ネイティブの音声素人の感想です)。
親戚が住む上越や九州南部の方言を聞いていると、標準語よりも母音の変化がはげしく、複雑に聞こえる。会話も、単語の伝達よりも相槌や語尾の微妙なニュアンスが大事そうだ。
さらに、その会話の内容も重要だ。「誰々さんがどうした」「お墓がどうした」「野菜が高い」「大河ドラマのだれだれ」といった、肯定も否定もしない、毒にも薬にもならないやりとり。
そこには攻撃性がなく、脳も強いて聞き入ろうとしない。ましてやそれが、3~6歳の幼児であれば、前提となるコンテキストも情報処理能力も持っていないのだから、ますます聞こうとはしないだろう。
もし、この「退屈な音響特性」を電子的に再現できたらどうだろうか。
意味のある言葉を録音し、子音を削ぎ落とし、フォルマントをいじって重ね合わせ、「架空の親戚」の声を作る。それを不規則なリズムで再生するプログラム。
それは、通知音や広告で疲弊した脳を、強制的にあの「冬の陽だまり」へと連れ戻す、最強のASMRになるかもしれない。
私は今、無性にその「退屈」を実装したくなっている。